画像出展:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/)
改めてカミュの生涯や名言を振り返ると今日も頑張ろうと思えます。
アルベール・カミュとは
 アルベール・カミュは1957年にノーベル文学賞を受賞したフランスの文学者であり思想家だ。
アルベール・カミュは1957年にノーベル文学賞を受賞したフランスの文学者であり思想家だ。
カミュは、フランス植民地であったアルジェリアで生まれ、大学卒業後は植民地体制下のアルジェリアの悲惨な実態を告発する新聞記者として活躍。
第二次世界大戦が勃発したころにパリに渡り作家活動を本格化するが、レジスタンスとしても行動していた。
『異邦人』『シーシュポスの神話』は戦時下で発表され、戦後は小説として『ペスト』を刊行、思想をまとめたエッセイ『反抗的人間』は、現代でも読み継がれている。
カミュの名言といえば「われ反抗す,ゆえにわれら在り」であり、彼の人生そのものが不条理への反抗だった。
彼の作品だけではなく、彼の行動すべてが、抽象的な理念ではなく、生物としてもっている生の感覚や直感を大切にしいた。
丁寧で誠実に生きてゆくことこそ人間らしい生き方であることを私たちに教えている。
今回はそれを以下の3つにまとめたい。
- 1)モラルとは自分でできることを見極めること、モラルを守るということは自分の職務を果たすこと。
- 2)不条理な現実を受け入れることなく、他者と連帯することで、孤独から抜け出して生を輝かせることができる。
- 3)「私は正義を信じる。しかし正義より前に私の母を守るであろう」正義は絶対ではない。
アルベール・カミュの生涯と人柄
1)アルベール・カミュの生涯
1913年、フランスの植民地であったアルジェリアのモンドヴィ(現ドレアン)近郊に生まれる。
農場労働者の父とスペイン系の母を持ち、兄とともに貧しい少年時代を過ごす。家には本が一冊もなく、字を読める人もいなかったという。
父はカミュの生まれた翌年に第一次世界大戦に出征し、マルヌ会戦で戦死している。
奨学金を得ることができたおかげで、1932年にアルジェリア大学に入学、文学を専攻する。
共産党員となるがアラブ人とフランス人の間で板挟みとなり党から除名された。卒業後は新聞記者となり、社会の不正を告発、第二次世界大戦の勃発に対しては平和主義を訴える。
当局は検閲を強めカミュの活動に制限を加え、ついには新聞の発行禁止とした。その責任をとらされ、カミュは記者を解雇される。
1940年、フランス・パリに移り記者の職を得るが、ナチスによるパリの占領のため長くは続かず、持病の結核の療養などでフランスとアルジェリアを行き来しながら、作品の執筆を続けた。
1942年に『異邦人』『シーシュポスの神話』を発表し文筆家としての地位を確立する。
この時期、アルジェリアに英米軍が入り、フランスからの行き来ができなくなる。
連合国によるパリ開放まではパリでレジスタンスの地下活動に身を投じ機関誌の発行に関わる。
この時期にサルトル、ボーヴォワールと親交を深める。
レジスタンス機関誌は、戦後も続き、カミュは編集長となる。
このころ占領時の対独協力者の処罰について世論は激しカミュは苦悩する。
1947年に『ペスト』を発表する。
この作品には戦中戦後の極限の精神状態でカミュがたどり着いた決意を見ることができる。多くの読者の共感を得てカミュの名を一層高めた。
同時にアルジェリアでは独立を渇望する民衆の活動が活発化し宗主国フランスとの対立が暴力的な色彩を帯びてくる。
理念とその実現を為の暴力を否定する立場のカミュは態度を明確化せず、臆病で卑怯者という評価を受け孤立した。
1952年には哲学的大著「反抗的人間」を刊行したが、賛否が大きく分かれ、盟友であったサルトルからは厳しい批判を受けた。
1957年にノーベル文学賞を受賞するが、フランスでは冷淡な反応であった。
アルジェリア独立戦争が激化する中でも沈黙を守ってきたカミュは、ノーベル賞の授与式において重い口を開いた。
「私は正義を信ずる。しかし正義より前に私の母を守るであろう」。
1960年に自動車事故で逝去。
持病の結核に苛まれながら自伝的小説『最初の人間』を執筆中であった。享年46歳。
連帯を望みながらの孤独な死であった。
2)アルベール・カミュの人柄
貧しい農場労働者であった父が戦争で亡くなり、カミュは父の顔を覚えていない。
夫を失ったショックで彼の母は難聴ととなり、生活に窮して実家を頼ることになる。その祖母の家もアルジェにある貧民街であった。
祖母は冷淡で押し付けがましく、母は寡黙で子供が愛情に飢えておかしくなっても不思議ではない。しかしカミュは少年らしい健康で生命力のある少年に育つ。
「私の少年期を支配していた太陽は、私から一切の怨恨を抜き取った」。
木曜と日曜にはサッカーに夢中になうような少年だった。
本が一冊も無いような家庭だったが、天授の才能は学校の先生の目に留まる程であった。
小学校の卒業後は就職するはずだったが、先生から中学・高校への進学を勧められ、奨学金を得て進学する。
裕福な家庭の子供が集まっている中で、共通の話題もなく孤独だったカミュはより一層、サッカーに打ち込んだ。
しかし17歳の少年にさらなる試練が襲う。
結核に罹り吐血し、その状態は死を覚悟するほどのものだった。
しかしそこにまた光を届ける人がいた。
哲学教師・グルニエが病床の彼に差し入れたのはリショーの小説、『苦悩』であった。
カミュはこの本により病と孤独に改めて向き合い生きることに希望をもった。
大学進学の気がなかったはカミュだったが、グルニエの影響の下はアルジェリア大学の文学部に進む。
グルニエの著書「孤島」の影響も大きく、カミュ自身が序文を寄せた。
グルニエ先生との交流は生涯続き、師からカミュへの追悼文はこの句で終わっている。
「小さな火花のつぎに大きな炎が続く」。
少年から青年への成長の過程は決して恵まれたものではなかったが、それは後に偉大なカミュの創作の出発点となった。
貧困、文盲で耳の遠い母親とその息子、そして、病。カ
ミュの作品はどれも同じ題材を繰り返し 扱っているとよく指摘されている。
カミュの創作の時間は限りない自分自身との対話だったのではないかと想像する。
極めて個人的に貧困、病気、そこで生じる孤独について考える、そして更に孤独を深める。
苦しくてもその問題を誰のせいにもせずに考える。
その結果として、この世界=不条理となる。だからカミュは他者の評価を顧みない。
サルトルとの論争、アルジェリア戦争に関する沈黙も理解できる。
カミュの人生は生きにくさを感じる世界に絶望せずに、他者との関わりの中で丁寧に自己と社会を作ろうとした軌跡のように私には感じられる。
教えられることが多い人生だと思う。
アルベール・カミュの名言・生き方から学ぶこと
 アルベール・カミュのお墓
アルベール・カミュのお墓
1)「子どもたちが責めさいなまれるように作られたこんな世界を愛することなどは、死んでも肯んじません」(『ペスト』におけるリウーの怒り)
『ペスト』に登場する神父はペストにより封鎖された市民たちに「わが兄弟たちよ、あなたがたは災いのなかにいます。そして、それは当然の報いなのです」と説教をした。そしてこう続ける。
「今日、ペストがあなたがたに関わるようになったのは、反省すべき時が来たということなのです。心正しい人は恐れることはありません。しかし悪しき人々は震えおののく必要があるでしょう。」
突然の災いを「天罰」だと語り、そこに必然があったかのように信じ込ませてしまう人が出てくることは私も身近な例で知っている。合理的な説明がなくとも、信じられない規模でふりかかってくる恐怖に遭遇すると、すっと心を支配され自分の頭で考えられなくなる言葉の危うさである。『ペスト』の劇中ではペストが少年の命を奪う場面があり、立ち会った神父に対し医師はこの子は何の故があって罰がくだったのかと問い、神への不信を表明したのである。
理念を敵とし命を大切にした、カミュの思想の柔らかさと苛烈さを良く表しているシーンである。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』でアリョーシャが全く同じことを言っていたことも特筆に値する。
2)われ反抗す、ゆえにわれら在り(『反抗的人間』)
『反抗的人間』という著作のなかで特に有名な一節である。「反抗は、すべての人間の上に、最初の価値をきずきあげる共通の場である。」とし、「反抗」を基盤として私たちは連帯しようということである。
ここで重要なのは反抗し連帯するとは、共同して戦うという暴力ではない。誤解を恐れずに言うと、正しいとか間違っているとかの外部の価値判断を自分の行動基準にあてはめようとする際に違和感を感じた時に、孤独から抜け出し他者と連帯して解決するのである。
カミュの幼少からの歩みをみれば、そのような思いに至ったということに不自然さは感じない。
サルトルをはじめとする当時の哲学者たちは実存主義を深化させることによって強烈な支持を得ていた。そこには理念が先に立つ政治的なイデオロギー持ち、積極的に実力行使をしてゆくことのみにより自己が作られるのだ。カミュはそれに与しない。それゆえサルトルとは『反抗的人間』を発表以来、関係を断った。今でもフランスの思想界においてカミュは無視されている。
フランス語の難しさはあるものの、カミュのこの言葉は私にとっては生きる指標となるものである。いくら合理的な理屈をたてても、言葉を積み重ねてもなにかしっくりこない、自分にはふさわしくない、似合わないと思うことを信じるな、その感覚を共有できる人との関係を大事にしろ、そんな風に解釈している。
理念に共鳴してはじめてうまくいくことも、途中で息苦しくなってくることがある。内向きに自分の思想を育て、丁寧に人と関わることはこの時代にはあわないかもしれないが、分断と局地化が進みぎすぎしした世界への反抗の方法として有効だと思う。
3)「私は正義を信じる。しかし正義より前に私の母を守るであろう」
苦労しつつも、自分の育ったアルジェリアに愛着が深く、追われるようにフランスに渡り活動の基盤を築いた後も、母の暮らす故郷には頻繁に帰っていた。
パリの社交界に嫌気が差して、恒久的にアルジェリアに戻ることを検討し、友人に転居先を探してもらう依頼をしたことさえあった。
戦前より続くアラブとフランスの対立がいよいよ激化しても、両者の対立は選挙により代表者を選び、民主的な方法によって解決できるだろうと考えていた。
フランス人が専制的に支配することはアラブにとっての不条理であり、100年以上暮らしてきたフランス人が故郷を追い出されることも不条理だ。
これに反抗し、暴力以外の方法での解決するために自分のできることをするというのがカミュの倫理であった。
不条理に反抗することは暴力を意味するということではなく、理念によって他方を打ち負かすことではないのだ。
愛する故郷の人々が誰も不条理の中で死ぬことがないことこそ、カミュの願ったことに違いない。
「私は正義を信ずる。しかし正義より前に私の母を守るであろう」とは、みんながそう思えば、子供や老人たちが先に死ぬような戦争状態にならず、別の方法での解決が図れるという思いを静かに表明したのである。
理念のためなら犠牲を厭わない、それを避ける者は歴史を作ることができないとする思想が支持されていた当時においては疑われるような発言であった。
レジスタンス運動の指導者であった彼はそう言ったのである。私はここにカミュの誠実さを見るのである。
『ペスト』でのタルーの言葉を思い出さないではいられない。
「さしあたって、僕は、自分がこの世界そのものに対してなんの価値もない人間になってしまったこと、僕が人を殺すことを断念した瞬間から、決定的な追放に処せられた身となったこと、を知っている」
徹底した孤独のなかで、嘆くこともない恨むこともなく、ただ内なる自分の声に耳を澄ませて、人々の生命のきらめきを最上の価値としたのがカミュの生き方であった。
彼の想像は異なり、その思想は再び歴史を動かせるような説得力を持ち始めているのではないかと思う。
アルベール・カミュの異邦人・ペスト・著書からしのぶ
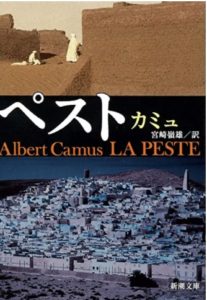 ある本によるとカミュの『異邦人』は20世紀でもっとも読まれたフランス語の書籍だという。『異邦人』のフランスでの発行部数は650万部で圧倒的な一位で、二位は同じカミュの『ペスト』。日本で言うと誰にあたるのだろう。
ある本によるとカミュの『異邦人』は20世紀でもっとも読まれたフランス語の書籍だという。『異邦人』のフランスでの発行部数は650万部で圧倒的な一位で、二位は同じカミュの『ペスト』。日本で言うと誰にあたるのだろう。
アルジェリア出身のフランス人の作家は終生、ナチスとの戦いの時期を除いて国家や民族という大きな物語においてはホームをもてない放浪者のようだった。その作家がフランスを代表する作品を残しているのはなにかひっかかるものがある。
私は独立した人間ではなく、いつも組織に従属して生きてきた。組織はそれぞれ違う原理で動き、そこにおける自分の価値も勝手に決められてしまう。なにかしらの違和感を感じ心がざわざわすることが沢山ある。そこには孤独が付きまとう。
自分は世の中のためになにができるのか、ということと、生きてゆくための金を稼ぐことや組織の中で認められることに悩まない人がいたとしても、それは稀だと思う。
多くの人は、抽象的な理念に共感してみたり、他人からの承認を集めたり、即物的な満足で孤独を紛らわしながら生きていたりするのかもしれない。
価値体系の大きな転換期に差し掛かり、これまでなんとなく躊躇していたようなことまで堰を切ったように変わり始めた。ある種の無力感、あるいは絶望感があり、強い不安からこれまでよりもよりストレスをため込んでしまうかもしれない。
私はカミュを思い出すことでそのような不安を癒している。内なる自分との対話を繰り返し、冷静に判断してゆくこと、そのことを他人と共有すること、これが始まりとなり連帯が生まれ孤独は解消されるというカミュのまとめてくれたことに価値を感じるのである。
これまでも自然にやっていたことなのかもしれないが、カミュのようにうまく言えなかった。多くの人にカミュを通じて知ってもらいたいと強く願う。













