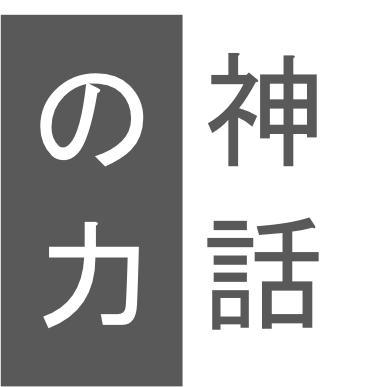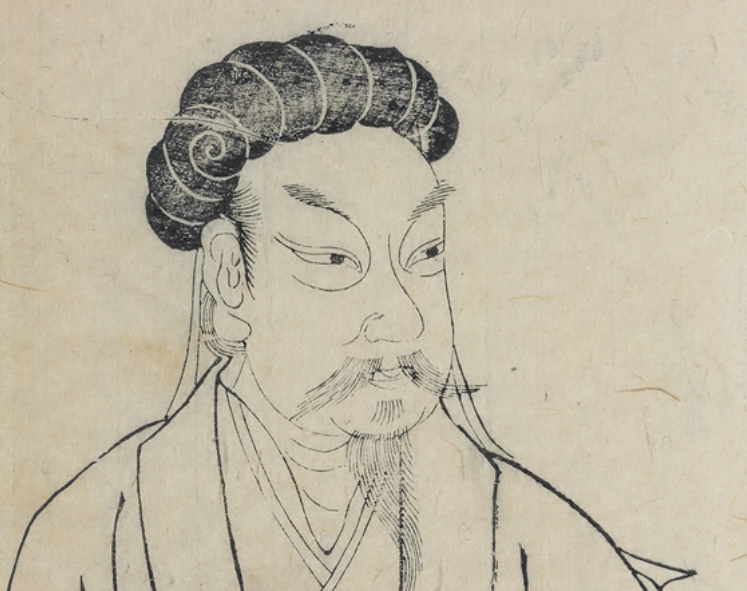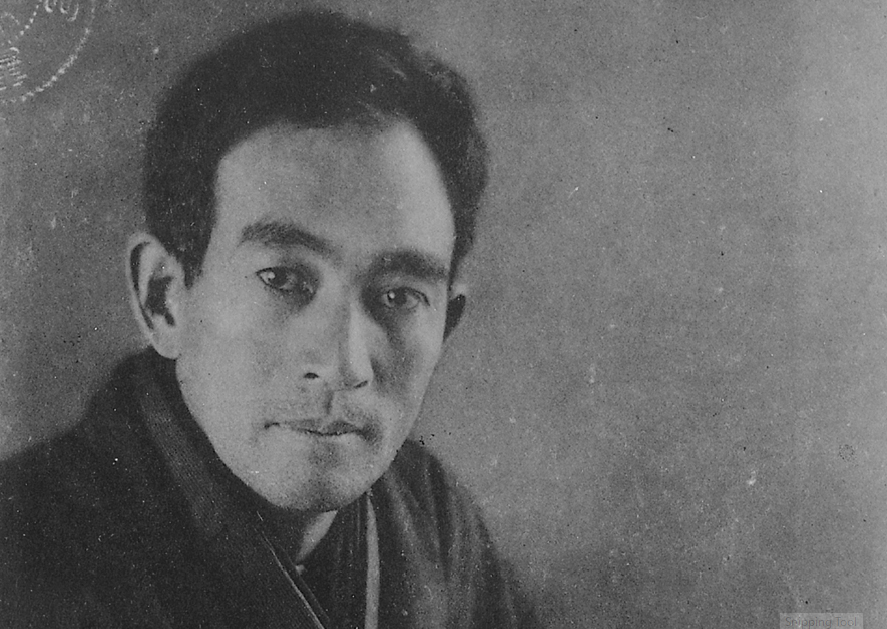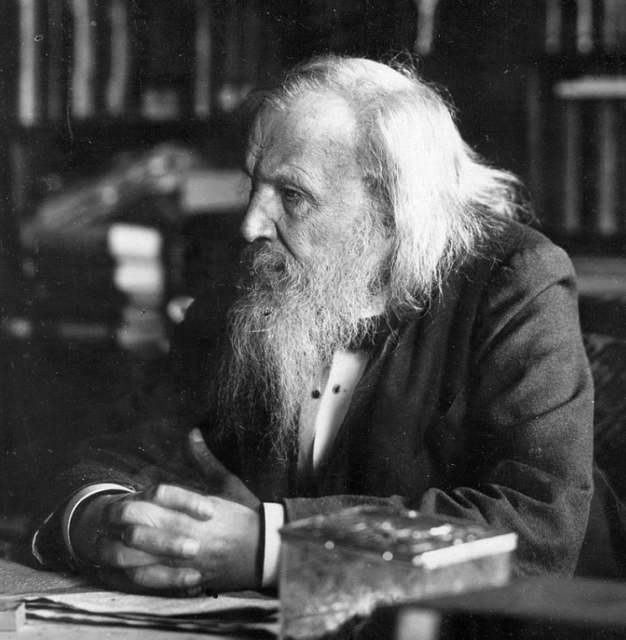こんにちは。ヒストリカルライターじぇむずです。
今回はをキルケゴールを語ります!
キエルケゴールは著名な思想家の一人としてその名前は聞く方は多いと思う。あなたもその一人だろうか?
「実存主義」の祖であり、
その後の「知」に大いなる先鞭をつけた“反骨の探求者”
偏屈、情緒不安定、素直すぎ、世渡りはものすごい下手(笑)
その分、何事に対しても徹底的に取り組み、世間全部を敵に回しても“真理への道”をたわめない。
元々口ばかり達者で多少、狂信的なところもあるが、どうしたことか求道の果てにその生き様は“妙なる美しさ”を放っていた。
『人生は、後ろ向きにしか理解できないが、前を向いてしか生きられない』
『人生の初期において最大の危険は、リスクを犯さないことにある』
どこまでも深みのある文言。
思わずリスクを取ってでも一歩踏み出したくなる。
彼が生前最もあこがれていた“キリスト”や“ソクラテス”同様”にしてまさに“真理”に殉じたその様。
ニーチェ、ヤスパース、サルトル、ハイデガーなどとなぜその系譜は繋がったのか。
生前、ほぼ報われることなく終わったが、なぜ死して後に大いなる潮流となっていったのか。
彼は何を残したのか。
哲学、思想を研究している人々だけでなく、ごく普通に生きている人々にぜひ一度は触れてほしい人物。
キルケゴールの生涯と人柄
1)キエルケゴールの生い立ち
本名セーレン・キエルケゴール。1813年デンマーク生まれの哲学者。その後、ニーチェ、ハイデガー、ヤスパース、サルトルなどと続いてゆく実存主義の祖と言われる。
ちょうど彼より少し前の時代に“理性”に重きを置くヘーゲル(1770-1831)の哲学が大変な流行を見せていた。が、セーレンはこれに若くして矛盾を感じ、「理性的な把握に逆らうもろもろの事実のなかでも最たるものが,自分自身のこの事実存在にほかならない」と
思いいたり,それを「実存」と呼び、おのれの思索の基盤として独自の探求の道をひた歩んでゆく。
『あれか、これか』『死に至る病』『瞬間』など数多い著作を発表。ただ、世間などに対して挑戦的なものも多く、様々なスキャンダルにも巻き込まれ、在世当時は芳しい評価を得られなかった。
1855年不遇のうちにこの世を去るが、その後次第に彼の遺したものは評価を集め、時代の一大潮流となってゆく。
2)キエルケゴールの人柄
哲学者としてはありがちなことかもしれないが、かなりの偏屈であり、一般受けは決してしない。
むしろ、「私はどうしても世間に嫌がられる得体のしれない何かを秘めているらしい」と自覚すらしていた。
何事にも突き詰める性向で、ただひたすら個人での研究に明け暮れ、社会のそこかしこと衝突しながら独立独歩の境地を深めていく。
その分情緒不安定で、容赦がない。
思いの果てに婚約したはずのレギーネに対して1年後突然、一方的に破棄。また、まだ売れる前のアンデルセンに対して彼の著作を「ケチョンケチョン」にしたこともある。
大学教授の不正を告発し、逆恨みされてひどい目に遭ったり、当時の国教会に真正面から異論をぶつけて、教会と国民の大半を敵に回してしまったりしている。
ニーチェと同じで幼少時かなり厳しく信仰をしつけられたためか、信仰心は終生非常に強かった。ニーチェは逆に旧来のキリスト教に対してかなり破壊的な言動を繰り返すようになるが。
ただ、既成秩序に対して挑戦的というのは彼と変わらない。
キエルケゴールは独自の“原キリスト教”的な解釈によって結局は当時の信仰の在り方に真っ向から立ち向かってゆく。
キルケゴールがわかる3つのエピソード
1)コペンハーゲン指折りの富商の息子。そのひねくれの過程
父ミカエルは元々貧農の出であるが、毛織物商として一代で立身し、コペンハーゲンでも指折りの富商となっていた。ゼーレンはその七人ある子供たちの末っ子。
コペンハーゲン大学に進学し、神学と哲学を修め、ベルリン大学に留学も果たしている。
次第に当時ヘーゲルやシェリングの理論に反発を強めるようになり、そんな最中父ミカエルがゼーレンに衝撃的告発をする。
キエルケゴール家は元七人子がいたが長兄ペーター以外はいずれも早く亡くなっている。
ミカエルは言った。
「私がまだ貧乏だったころの話だ。なんでこんな苦境に遭わなきゃならんのか、という思いを抑えられなくなってしまってね。呪ったんだよ。神を」
「もうあんたなんか信用しない。こんなに信奉してるのに。小さいころからずっとだ」
「なんだ。何の不足があるんだ、あんたは」
「俺はあんたと絶縁したっていい。それで暮らしが豊かになるんなら」
「そうしたらだ。不思議なことに急に商売が軌道になりだしやがった。あっという間だ」
「ただな。よく聞け。あるんだよ。呪いは」
「神は呪っているんだ。俺のことを。俺と血のつながるものたちすべてを」
「みんな死ぬんだ。34歳までに。キリストの磔刑に処されたあの歳までに。そして俺だけただ一人生き残り、思い知るんだ……」
彼はこの時のことを『大地震』と呼んだ。そして以後打って変わって放蕩にふけるようになる。
2)レギーネとの大恋愛
何せ金と時間はあるのでやりたい放題、遊び放題。そのすっかり頽廃しきった暮らしのしりぬぐいをするのはいつも父家。しかし、当のセーレンは全然やめる気がない。長年培った素養から小難しい言葉をこねくり回し、そういった仲間連中と日がな夜な夜な……。
そんな彼にも気になる少女が現れた。レギーネである。
レギーネはかなりの名家の令嬢であり、歳は十歳もかけ離れている。ただセーレンは彼女への慕情やみがたくついに求婚するが、レギーネの実家に猛反発される。
セーレンはそこを持ち前の一途さでごり押しし、婚約までこぎつけるが、そのわずか一年後、セーレンは突如この契約を一方的に破棄する。
その理由については様々な憶測があるが、まだ確たるものはわからない。
どうせ間もなく死にゆくであろう自分では、と急に慙愧の念がこみあげたのだろうか。
3)『自らの挫折の中に信仰を持つ者は、自らの勝利を見出す』
やがて、セーレンは堅気として牧師になることを志す。が、そんな矢先である。
セーレンは元学友であったある大学教授の不正を暴き立て、それが逆恨みされてしまう。この学友と後ろでつながっていたある週刊新聞社によって散々にさらし者にされ、行く先々で人々に後ろ指をさされ、あることないこと罵り囁かれ、とうとう牧師への道をも頓挫してしまう。
マスコミの弊害を100年以上前にまともに味わった男。
ただこれがセーレンにとって、いや世界にとって“大いなる画期”となった。
とうとう彼は自宅に籠り、自分の研究に明け暮れるようになる。
宅から宅へと転居を繰り返し、作品によって多くの筆名を多用。
一度は修道士生活をまねてみるが、すぐに諦めた。
キエルケゴール名言と最期
キルケゴールの名言
ここまでたどってみるといったいどこが「偉人」なのかわからない、本当にただの偏屈者、破綻者だが、彼の凄みはここから。さあ、ご堪能あれ。その珠玉の名言集。
『行動と情熱がなくなると、その世界は、妬みに支配される』
『もしもあなたが私にレッテルをはるなら、それは、私の存在を否定することになる』
『祈りは神を変えず、祈る者を変える』
『心の純粋さとは、ひとつのものを望むことである』
『しばらく二人で黙っているといい。その沈黙に耐えられる関係かどうか』
『自らの挫折の中に信仰を持つ者は、自らの勝利を見出す』
『人間は思想を隠すためでなく、思想を持ってないことを隠すために語ることを覚えた』
『孤独とは生命の要求である』
『人生は、解かれるべき問題ではなく、経験されるべき現実である』
『めったに使われない思考の自由の代償として、人々は言論の自由を要求する』
『哲学は踏み出す一歩一歩ごとに皮を一枚ずつ脱ぎ捨てるのだが、愚かな弟子どもは、その皮の中へもぐり込んでゆく』
『人を誘惑することのできないような者は、人を救うこともできない』
『あらゆる人生は反復である。追憶は後方へ向かって反復されるが、本当の反復は前方に向かって反復される』
『臆病の虫に取り付かれると、その人はよきことを行わなくなる』
『苦難の道は永くもあれば、また暗くもある。次第に明るくなるような道は別の道である』
『忘れるということができない者は、分別のある者にならない』
『皮肉には主観性の資質がある』
キルケゴールその最期
いよいよ信仰の在り方をめぐって国教会と対立。彼はあくまでその融通無碍なさまを酷評し、元来のキリスト的信仰を呼び覚まそうとするが、ほぼ誰にも顧みられない。
ここがなんとも彼らしいところだが、当時国教会に反発するまたほかの識者がいたのだが、セーレンにしたら「生ぬるい」。
“敵の敵は味方”という発想は彼にとって子供だましぐらいの価値しかない。だから、彼に対しても平然と論難、バッサリやった。
やがてセーレンはただ研究に没頭する傍ら亡き父の遺産を次第にすり減らしてゆく。ちょうど財産のほぼすべてのなくなった1855年コペンハーゲンの町で行き倒れになり、それが元で一か月後に亡くなる。享年42歳。
狂信的だが美しい言葉・文章を遺したキルケゴール
筆者から見てもやりすぎでついていけないところがある。ちょっと狂信的でもある。
ただ、彼の遺した言葉・文章はあまりに美しい。
超一流の哲学者・思想家の遺す言葉・文章は古今東西を問わずいずれも文学的にも信じがたいほどの光彩を放っているが、彼もまたその一人。
私が特にお勧めするのが彼の晩年の著作『瞬間』。
健気で、一途で、……。
あれだけインテリでトリッキーなばかりの人間だったはずなのに、なぜだろう。
彼は他人に容赦がない分、自分にも容赦がない。
そして、もともとただの口先人間だっただけの自分が知らぬ間にそちら側に立とうとしているのが自覚された。彼の晩年はまさに彼の人生の集大成「最後へ至る階段」なのである。
彼の最後の生き様、そして死に様は確かにあまりにも“キリスト的”だった。
そして、結局彼の先鞭をつけた事業、事績は後代にあまりに偉大なる遺産となった。
先に述べたニーチェやハイデガー、サルトルら。あるいは世界的文豪のカフカやカミュ、大江健三郎、と彼がいなければこの系譜は続いたであろうか。
いや、私は哲学や思想を専攻する学者や文学者のみならず、一般の人々にこそ触れてほしい。
その生き様や名言だけでもいい。